電験三種 法規 問題チェック25
全国の電験男子・電験女子の皆さん、こんにちは!資格合格支援スクール【能セン】のPRキャラ『ノウセンちゃん』です!
電験三種に合格するためには、まず基礎をしっかり固めることが大切です。特に法規は、実務的な知識が問われる科目であり、法令や制度の理解が合否を左右します。電気事業法や電気設備技術基準、保安規定など、重要な法律・規則を正しく把握することで、実務に直結した力も身につきます。
数字や公式に頼るだけでなく、条文の意味や背景をしっかり理解していけば、法規の得点力は着実に上がります。焦らず一歩ずつ取り組むことで、合格への道が開けてきます!
本サイトでは、電験三種の「法規」科目における基礎的な問題を20問厳選し、理解度をチェックできるようにしました。出題頻度の高い条文や、過去問で狙われやすいポイントを中心に構成しており、試験対策の土台をしっかり固めることができます。
✅ こんな方におすすめ!
- 電験三種法規の勉強を始めたばかりの方
- 法規の基本用語や条文をしっかり理解したい方
- 短時間で効率よく重要ポイントを確認したい方

何事も基礎が大切なのだ! 最後まで諦めずに、全問正解を目指すのだ!
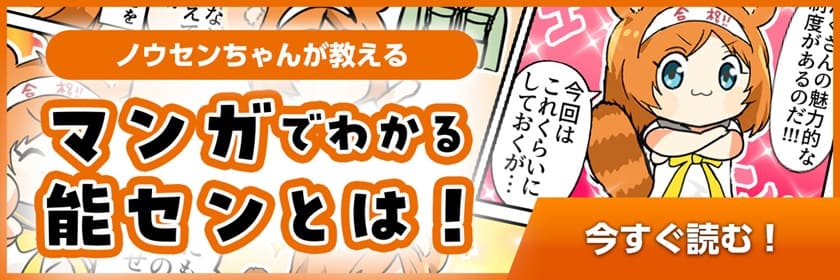
問題1 事業用電気工作物の定義に関する問題
電気事業法に基づき、事業用電気工作物に該当するものは次のうちどれか?
① 一般家庭内の電気配線設備
② 自家用発電設備を持つ工場の電気設備
③ 家庭用の太陽光発電パネル(10kW未満)
④ コンセントにつなぐだけの携帯充電器
問題2 電気主任技術者の選任要否に関する問題
電気主任技術者の選任が不要な場合として正しいのはどれか?
① 自家用電気工作物を設置するビル(高圧受電)
② 一般用電気工作物を設置する住宅
③ 500kWの自家用発電設備を持つ工場
④ 電力会社が管理する変電所
問題3 電気工作物の工事と届出に関する問題
次のうち、電気事業法において電気工作物の工事の届け出が必要となる場合として適切なのはどれか?
① 低圧配線のコンセントを1つ増設する工事
② 自家用電気工作物の新設工事
③ 家庭用電球をLEDに取り替える作業
④ 家庭用エアコンを買い替える工事
問題4 電気用品安全法における特定電気用品の分類
電気用品安全法(PSE法)において、特定電気用品に分類されるものはどれか?
① 延長コード
② 冷蔵庫
③ 電気こたつ
④ 高圧ガスを使用する溶接機
問題5 電気事業法における保安監督者の役割
電気事業法における保安監督者の主な役割として適切なものはどれか?
① 電気料金の徴収を行う
② 電気設備の設計を担当する
③ 電気工作物の保安の監督を行う
④ 電力の需給調整を行う
問題6 感電防止措置に関する問題(労働安全衛生法)
労働安全衛生法に基づく感電防止のための措置として義務付けられているものはどれか?
① 作業員に作業日報を毎日提出させる
② 作業員の健康診断を年1回実施する
③ 作業員に絶縁抵抗計の使い方を教える
④ 帯電部に近接して作業する際は停電または活線防護を行う
問題7 一般用電気工作物の工事に必要な資格
電気事業法に基づき、一般用電気工作物の工事を行うために必要な資格はどれか?
① 第二種電気工事士
② 第一種電気工事士
③ 電気主任技術者
④ 工事担任者
問題8 保安規程の作成義務に関する問題
電気事業法に基づき、保安規程を作成し届け出なければならないのはどれか?
① 一般家庭のみを対象とする電気工事業者
② 自家用電気工作物を設置している事業者
③ 電気工事士試験の受験者
④ 家電販売店
問題9 消防法における非常用予備発電装置の点検頻度
消防法に基づき、非常用予備発電装置の定期点検を行うべき頻度として正しいのはどれか?
① 毎日
② 毎月
③ 年2回以上
④ 3年ごと
問題10 力率改善による電力損失低減
高圧受電設備(6.6kV、契約電力500kW)が、平均力率80%で運用されている。
力率を95%に改善すると、皮相電力(kVA)はおよそ何%減少するか?(力率改善前後の有効電力は同じとする)
① 約10%
② 約12%
③ 約15%
④ 約20%
問題11 電気料金計算
高圧受電契約の工場で、契約電力が400kW、当月の使用電力量が120,000kWhであった。
電力会社の料金単価は次のとおりとする。
- 基本料金:1,650円/kW
- 電力量料金:15.20円/kWh
このとき、当月の電気料金として正しいものはどれか?
① 約2,160,000円
② 約2,280,000円
③ 約2,340,000円
④ 約2,460,000円
問題12 過料計算
ある事業者が、自家用電気工作物の設置に関して電気事業法に基づく工事計画届出を行わなかった。
この場合、課せられる過料の上限額として正しいのはどれか?
① 10万円
② 30万円
③ 50万円
④ 100万円
問題13 絶縁抵抗の法定値
低圧の電路で対地電圧300V以下の屋内配線を布設する場合、電気設備技術基準に基づく絶縁抵抗の最小値として正しいのはどれか?
① 0.1 MΩ
② 0.2 MΩ
③ 0.4 MΩ
④ 0.5 MΩ
問題14 電気設備の接地工事における安全目的
電気設備の接地工事に関して、安全確保のために最も重要な役割はどれか?
① 電気機器の性能向上
② 漏電や感電の防止
③ 電力の安定供給
④ 電気料金の節約
問題15 電気主任技術者の作成書類に関する問題
電気事業法において、電気主任技術者が作成しなければならない書類として正しいものはどれか?
① 電気設備の保安規程
② 工事計画届出書
③ 保安監督報告書
④ 年次報告書
問題16 自家用電気工作物の定義に関する問題
電気事業法における「自家用電気工作物」とはどれを指すか?
① 電力会社が送配電を行う設備
② 一般家庭の低圧配線設備
③ 事業者が自己の業務用に設置する電気設備
④ 商用電力の供給設備
問題17 感電防止の基本対策に関する問題
電気設備の保安管理において、感電事故を防止するために最も基本的な対策はどれか?
① 絶縁の強化
② 電力の安定供給
③ 電気料金の適正化
④ 工事計画届の提出
問題18 電気主任技術者の事故対応に関する問題
電気事業法に基づき、電気設備の事故発生時に電気主任技術者が行うべき対応として適切なものはどれか?
① 事故の原因調査と報告書の作成
② 電気料金の請求調整
③ 新規契約の申請
④ 設備の新設計画の立案
問題19 電気工作物の工事に関する届出手続き
電気事業法において、電気工作物の設置や変更を行う場合に必要な手続きはどれか?
① 電気主任技術者の選任届出
② 工事計画の届出
③ 保安規程の変更届出
④ 電気料金の支払い申請
問題20 電気主任技術者の資格要件に関する問題
電気事業法に基づき、電気主任技術者が最低限保持しなければならない資格はどれか?
① 第二種電気工事士
② 第一種電気工事士
③ 電験三種(第三種電気主任技術者)
④ 技術士(電気部門)
問題21 遮断器の設置目的に関する問題
高圧または特別高圧の電路に施設する遮断器について、法令で定められている設置目的として正しいものはどれか?
① 電路の電圧を一定に保つため
② 電路に流れる電流を常に監視するため
③ 過電流や短絡などの異常が発生したときに電路を遮断するため
④ 電気設備の接地抵抗を測定するため
問題22 避雷器の設置目的に関する問題
避雷器を高圧または特別高圧の電路に設置する主な目的として正しいものはどれか。
① 電路に流れる負荷電流を調整するため
② 落雷などによる異常電圧から電気設備を保護するため
③ 電路の電圧を常に一定に保つため
④ 接地抵抗を低減するため
問題23 非常用予備電源の設置目的に関する問題
病院や劇場などの施設に非常用予備電源を設ける主な目的として正しいものはどれか。
① 電力会社からの電気料金を節約するため
② 停電時にも安全に必要な電力を供給するため
③ 常に電圧を安定させるため
④ 電気機器の寿命を延ばすため
問題24 電線の太さを決定する条件に関する問題
電線の太さ(断面積)を決める際に、法令で最も基本的に考慮すべき条件はどれか。
① 電線の色の種類
② 電線の許容電流
③ 電線の購入価格
④ 電線の敷設距離
問題25 漏電遮断器の設置目的に関する問題
漏電遮断器(ELB)を低圧電路に施設する主な目的として正しいものはどれか?
① 電路に流れる電流を常に一定に保つため
② 過電流による電線の焼損を防ぐため
③ 漏電による感電や火災を防止するため
④ 雷による異常電圧を避けるため
【応用問題】高圧電路の1線地絡電流計算に関する応用問題
高圧受電設備において、対地電圧 6.6 kV の電路に 1 線地絡事故が発生した。
このときの地絡電流を求めるために必要な条件として最も適切なものはどれか。
① 電源変圧器の容量と負荷電流
② 電源側の短絡容量と系統の対地静電容量
③ 避雷器の制限電圧と接地抵抗値
④ 漏電遮断器の動作電流値と定格遮断容量
解答・解説
問題1 ② 事業用電気工作物とは、電気事業に関係する工作物、または自家用電気工作物のことであり、主に電気事業者や自家発電を行う企業などが保有する設備を指します。一般家庭の設備や小規模な発電設備(10kW未満の太陽光など)は対象外です。
問題2 ② 電気主任技術者は、自家用電気工作物を設置している施設では原則として選任が必要です。しかし、一般用電気工作物(主に住宅などの低圧設備)は、選任の対象外です。
問題3 ② 電気事業法では、自家用電気工作物の設置、変更、移転、廃止などには届け出または届出書類の提出が必要です。一方で、低圧家庭用の簡易な工事や器具の交換にはそのような届け出は不要です。
問題4 ① 電気用品安全法では、「特定電気用品」と「特定以外の電気用品」に分類されます。延長コード(電源コードセット)は感電や火災リスクが高いため、「特定電気用品」に該当します。冷蔵庫や電気こたつなどは「特定以外の電気用品」です。
問題5 ③ 保安監督者は、電気事業法に基づき電気工作物の保安(安全管理)を監督・維持する責任者です。料金徴収や設計、需給調整はそれぞれ別の担当部署や職種の役割となります。
問題6 ④ 労働安全衛生規則では、感電事故防止のため、停電作業または活線防護の実施が義務付けられています。
日報提出や健康診断は別の安全管理規定で定められており、感電防止措置の直接的な義務ではありません。
問題7 ① 一般用電気工作物(住宅や小規模店舗などの低圧設備)の工事は、第二種電気工事士の資格で施工可能です。第一種電気工事士は高圧や自家用設備も含む広い範囲を扱えますが、一般用のみであれば二種で十分です。
電気主任技術者は工事ではなく保安管理、工事担任者は通信回線系の工事資格です。
問題8 ② 電気事業法では、自家用電気工作物を設置する事業者は、電気工作物の保安を確保するための保安規程を作成し、経済産業大臣(または所轄産業保安監督部長)に届け出る必要があります。一般家庭のみや受験者、販売店にはこの義務はありません。
問題9 ③ 消防法施行規則では、非常用予備発電装置(防災用非常電源)の点検は6か月ごとに1回以上行うことが義務付けられています。これにより、年2回以上の点検が必要です。
問題10 ③ 力率改善は契約電力(kVA)を減らす効果があり、基本料金削減や損失低減に直結します。電験三種法規では、このようにkWとkVAの関係を計算する力が頻出です。
問題11 ④ 法規では、契約電力×基本単価+使用電力量×従量単価で計算する問題が頻出です。この計算は時間短縮のため、暗算や筆算を素早くできる練習が効果的です。
問題12 ② 電気事業法では、工事計画届出や工事完了届出を怠った場合、30万円以下の過料が科せられます。刑罰(懲役や罰金)ではなく行政上の過料である点もポイントです。法規試験では、条文の金額や期間を問う問題が毎年数問出題されます。
問題13 ②本問は「低圧の電路で対地電圧300V以下の屋内配線」とあり、対地電圧150V以下かどうかの条件が示されていません。したがって、より高い基準である「150V超~300V以下」の区分に該当し、最小値は0.2 MΩとなります。
問題14 ② 接地工事は、電気設備で万が一漏電が発生した際に、漏れた電流を安全に大地に流す役割を果たします。これにより、人体が触れても感電しにくくなるほか、火災の発生を防ぐ重要な安全対策となります。そのため、電気設備の安全管理において最も基本かつ重要な措置の一つです。
問題15 ③ 電気主任技術者は、電気設備の保安監督に関する状況を報告するために定期的に保安監督報告書を作成し、所轄官庁へ提出する義務があります。他の書類は、事業者や工事業者が作成・提出するものであり、主任技術者の直接の作成義務はありません。
問題16 ③ 自家用電気工作物とは、電力会社以外の事業者が自らの業務で使うために設置・管理する電気設備を指します。一般家庭の設備や電力会社の送配電設備は該当しません。
問題17 ① 感電防止の基本は、電気が人に直接流れないように絶縁をしっかり行うことです。これにより、人体が触れても安全が保たれます。他の選択肢は感電防止には直接関係しません。
問題18 ① 電気主任技術者は事故発生時に、事故原因を調査し、保安監督者や所轄官庁に報告する責任があります。事故の再発防止と安全確保のために重要な役割を担っています。他の選択肢は事故対応の役割ではありません
問題19 ② 電気事業法では、電気工作物の新設や変更を行う際に、事前に工事計画を所轄の監督官庁に届出ることが義務付けられています。これにより、安全性や適法性の確認が行われます。他の選択肢は手続きの一部ですが、工事計画届出が工事実施の前提となります。
問題20 ③ 電気主任技術者として選任されるためには、少なくとも第三種電気主任技術者(電験三種)以上の資格が必要です。第一種や第二種電気工事士は工事資格であり、主任技術者の資格要件とは異なります。
技術士は別の国家資格で、主任技術者資格とは直接関係ありません。
問題21 ③ 遮断器は電路に異常が発生した際、安全に電流を遮断するために設けられます。電圧の安定や監視、接地抵抗の測定といった役割は遮断器の本来の目的ではなく、誤りです。電気設備技術基準でも、高圧・特別高圧の電路には必要に応じて遮断器の設置が義務付けられています。
問題22 ② 避雷器は、落雷や開閉サージなどで発生する異常電圧を大地に逃がし、電気設備を保護するために設置されます。負荷電流の調整や電圧の安定保持、接地抵抗の低減といった役割は避雷器の目的ではありません。
問題23 ② 非常用予備電源は、停電などで通常の電源が失われた場合に、照明・火災報知設備・避難設備など、人命にかかわる重要設備へ電力を供給することを目的としています。電気料金の節約や機器寿命の延長は目的ではなく、電圧安定は通常の電源設備で行われる機能です。
問題24 ② 電線の太さは、その電線に流せる最大電流(許容電流)によって決まります。許容電流を超える電流が流れると発熱により絶縁劣化や火災の危険が生じるため、電気設備技術基準では適切な断面積を選定することが義務付けられています。電線の色や価格、敷設距離は設計上の考慮事項にはなりますが、法規上の基本的な選定条件ではありません。
問題25 ③ 漏電遮断器は、電路から大地へ電流が漏れる「漏電」を検出し、自動的に回路を遮断することで感電事故や漏電火災を防止するために設置されます。過電流保護は配線用遮断器、雷サージの対策は避雷器が担う機能であり、ELBの目的ではありません。
応用問題 ② 高圧系統における 1 線地絡事故時の電流は、主として 系統の対地静電容量 と 電源の短絡容量 に依存します。
・対地静電容量が大きいほど、地絡電流は増加します。
・短絡容量は系統のインピーダンスを反映し、地絡電流の大きさを左右します。
一方で、負荷電流や変圧器容量は直接関係せず、避雷器や漏電遮断器の定格値も地絡電流計算の条件とはなりません。このあたりは電験三種法規の中でも難度が高いテーマ(電技解釈・地絡電流計算)で、理解しているかが差がつく部分です。

もっと詳しい解説が知りたい方はAIさんに聞くと教えてくれるのだ/
令和8年度 受講受付中|今からでも間に合う!

第三種電気主任技術者の最短合格を目指すには、
能センの【 通学講座 】【 オンライン講座 】【 通信講座 】が最適解!
業界トップのわかりやすさ、受講生満足度が97%!!
まずは【お問い合わせ】や【資料請求】から始めてみませんか?
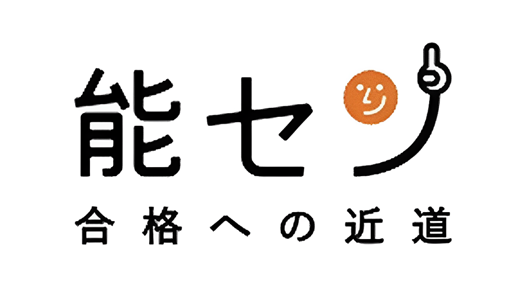
皆様が一日も早く電験三種に合格されることを楽しみにしております。
資格合格支援スクール【能セン】



